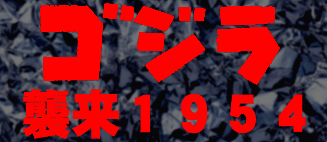
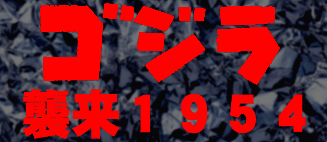
1 始まりの日
昭和27年9月24日 八丈島南方沖
その異変が確認されたのは、9月の初めのことだった。紺碧の海は赤錆を一面に流したかのような色へと変わり、大量の魚の屍骸がそこかしこに浮き上がっていた。
八丈島の漁師からの通報を受けた海上保安庁水路部は、直ちに調査船第五海洋丸を現地へと派遣した。第五海洋丸には船員や専門家、合わせて31名が乗りこんでいた。「見てください。海水温が異常に上昇しています」「こちらもだ。見たまえ、酸性値が尋常ではないよ」海洋調査の専門家たちはそれぞれ観測機器を操作し、そこから得られた観測結果を検討しあった。
「これは、海底火山活動と考えて間違いないでしょう」「うん、この海の底で昭和新山のときのような活発な火山活動が進行していると見ていいね」遡ること8年前、北海道の洞爺湖畔で突如噴火活動が起こり、新しい火山が誕生していた。その火山は昭和新山と名づけられていた。
「どうしましょう?このあたりの水域は危険ですよ。少し離れたほうがいいのではないですか?」水測員が、専門家たちに向かって尋ねた。「このまま進んで、下からドカン、なんてことになったら皆お陀仏ですよ」
「そうだな。しかし、折角海底火山の噴火活動を観測できる機会だからね。君、こんな機会はめったにあるものではないよ」
年かさの専門家が、好奇心いっぱいの顔つきで水測員に言った。
「昭和新山のときは、あんなご時世だったからね、満足に調査などできやしなかった。だが、ここでは・・・」
調査員がそう言いかけたとき、海底からドドドッと鈍い振動が船に伝わってきた。
「調査も大切ですが、自分らには乗員の命を守る義務がありますので」水測員は、船の揺れに足をとられ尻餅をついたその専門家に向かって言った。
「先生、大丈夫ですか?」年若い調査員が、専門家を助け起こそうと手を出した。「いや、大丈夫だ。それより機械がちゃんと固定してあるか見ておきたまえ。倒れて壊れたりしたら調査活動が台無しだからね」
専門家は立ちあがって、尻の汚れをパンパンと払った。海底で、それは目覚めた。遥かな昔に生を受けたそれは、しばらく海の王者として君臨した後に永い休眠期に入りこの海底で眠りを貪っていたのだ。だが、噴き出す硫黄ガスと高熱の海水とがその永い眠りを覚ましてしまった。
それは、休眠期の間その体躯を包んでいた蛹とも卵ともつかぬ軟らかな殻を脱ぎ捨て、海水の中へとその身を漂わせはじめた。「船長、どうしましょう?やはりこれ以上この水域に留まるのは危険ですよ」操舵手が、双眼鏡で前方に立ち上る噴煙を観測している船長に言った。「船体にも悪い影響がでるかも知れません。なにせ、海の底から酸が涌き出ているような状態なんですから。それにこの臭いときたら、頭が変になりそうですよ」
「ああ、このままここにいる訳にはいかんな。あの先生たちには悪いが少し離れたところから観測してもらうか」
双眼鏡を眼から離した船長も、先ほどから操舵室に充満している硫黄の臭いには辟易していた。
「よし、この水域から離れる。機関全速、面舵一杯!」船長は伝令管に向かって命令を下した。船のエンジンが出力をあげ、船全体を振動が包んだ。甲板から海水面の写真を撮っていた調査員が、船が海域から離れつつあることに気がついた。鼻と口とをタオルで覆っていたがそれでも硫黄の臭いは強烈で、その調査員の目からは先ほどから涙がこぼれていた。
「やれやれ、これで少しはこの臭いから逃げられるな」彼は赤錆色の海を見ながら一人呟いた。と、その海面下で何か黒い影が動いたのが一瞬見えたような気がした。
「あれ?」調査員は涙をこすり、もう一度海を見た。だが、赤錆色の海面以外何も変わったものは見えなかった。「気のせいか・・・?」彼はあたりの海面を見渡し、首を捻った。「船長、もう後1時間でいいから、この水域を調べさせてもらえんかね?」年かさの専門家は海面を指差して、船長に依頼した。
「日本近海で海底火山の活動調査が出来る機会など滅多にないのだよ。それは君も判るだろう?」
「それは、判ります。しかし、これ以上この海域にいることは危険なんです。私にはこの船を守り皆さんを無事に連れ帰る義務がありますので」船長も専門家も、互いの意見が職務への責任から出ていることは充分弁えていた。だが、船においては船長の判断のほうが優先される。専門家も長い海洋調査活動の経験からそのことは判っていた。しかし、海底火山の噴火など彼の一生において何度でも経験できるものではない。その事が彼を頑固にしていた。
「では、あと30分、30分でいいから頼むよ。危険な兆候が出てきたらすぐに調査を打ちきるから。それならば良いだろう?」専門家は船長に食い下がった。
「駄目です。許可できません!」船長も負けずにやりあった。
その時だった。船全体がエンジンの振動とは違う激しい揺れに包まれたかと思うと、たちまち船内のあらゆる物がそこらじゅうに転がりはじめた。もちろん人もその例外ではなかった。
「うわあ!」「何だ!噴火がはじまったのか?」船の乗員達は手近なパイプなどにつかまり、身体が飛び跳ねるのを防いだ。
「何があった!?各員、被害を報告しろ!機関室、大丈夫か?」船長が伝令管に向かって叫んだ。激しい揺れは、機関室も同様に襲った。だが、機関室の状況はもっと深刻だった。船体の一部に亀裂が生じたらしく、そこから海水が噴き出し始めていたのだ。
「機関室、浸水がはじまりました!保全要員をよこして下さい!」機関員はすでに腿のあたりまで水に浸かりながら、伝令管に叫び返した。「機関室浸水だ!保全要員は機関室へ向かえ!他に被害はないか!?」船長は次々に伝令を出した。「先生、火山が噴火したのか?」船長は専門家に向かって怒鳴るように尋ねた。
専門家は海面を見た。だが、海は先ほどと変わらぬ赤錆色をしていたものの、特に激しい変化はしていなかった。
「おかしい。噴火がはじまったのなら海からガスが吹きあがるはずだ?火山性の地震だったのか?いや、それでは船体に亀裂ができるはずが・・・」専門家も、揺れの原因を特定できなかった。
「せ、船長!右舷前方に岩礁・・・、いや、あれは!」操舵手が叫んだ。操舵室にいた全員が右舷を見た。そこには、岩のような黒い塊が波間に見えていた。そしてそれは船に向かってぐんぐんと近づいていたのだ。
「取り舵だ!避けろ!」船長が操舵手に叫び返した。操舵手はあわてて舵輪を回した。
「先生、岩礁が動いています!こっちに近づいてくる!」調査員が悲痛な叫び声を上げた。「馬鹿な!岩礁が動くものか!何なんだあれは!?」船に吸い寄せられるように近づいてくる黒い塊に恐怖し、専門家も叫んでいた。
「ああっ!接触します!」船員が叫ぶと同時に、再び激しく船が揺さぶられた。今度は乗員全員が床や壁にしたたかに打ちつけられ、何人かは昏倒して意識を失った。
船長も頭を何かにぶつけ、額から顔にかけて血が流れ始めた。「船長!今ので右舷にも亀裂が!浸水が激しくなっています!」
船員の声が伝令管から響いた。
「通信室!SOSだ!おい、救命艇を用意しろ!乗員は全員甲板に集合だ!」船長は手のひらで顔の血を拭いながら怒鳴った。
「怪我人を運べ!ぐずぐずするな!」海底火山に充満したマグマは、ついに岩盤を押し退け吹きあがった。第五海洋丸はそのすぐ近くの海上にいた。
地の底から響くような振動が船を揺さぶった。「ま、またか!」「いや、違う!これは、これは地震の揺れだ!」
調査員達は真に恐怖した。遂に海底火山の噴火が本格的にはじまったのだ。
第五海洋丸の前方の海面が突如爆発するように吹きあがった。第五海洋丸は嵐の中の木の葉のように激しく翻弄された。海中を激しい勢いで駆けあがってきたマグマは第五海洋丸の機関室部分を直撃した。そのマグマの熱で船体はあっという間に裂け、さらにディーゼルオイルに引火した。
「船長ー!」操舵手が恐怖の面持ちで船長に振り向いた。それとほぼ同時に第五海洋丸の船体が爆発し、バラバラになった船体はあっという間に乗員と共に海に沈んでいった。後にこの新しい海底火山は「明神礁」と名づけられ、調査中に爆沈し乗員全員が死亡した第五海洋丸の悲劇はしばらく新聞やラジオを賑わせた。だが、第五海洋丸の乗員が見た謎の黒い塊は誰にも気づかれることなく、いずこかへ消え去っていた。
2 「ブラボー」
1952年(昭和27年)11月1日 南太平洋マーシャル群島 エニウェトク環礁
明神礁に活動により目覚めた「それ」は、休眠前と同じく海の王者として君臨するように太平洋を回遊し始めた。
休眠前と変わっていたのは、マリアナやレイテといった島々の沖に数多くの鉄屑が沈んでいたことだったが、その鉄屑は海洋生物を育む温床となり、この海域は以前にもまして「それ」にとって、豊富な餌場となっていた。
「それ」は食べ物の豊富なこの海域にしばらく留まっていた。「それ」は最初この美しい珊瑚礁のやや南方にある同じような環礁を訪れた。その環礁には他と同じように数多くの鉄屑が沈んでいたのだが、何故か他の鉄屑とは違い生物の存在が見当たらなかった。
餌がいないと知った「それ」の頭上でそれは不意に起こった。突然激しい光が頭上から差したかと思うと、ものすごい振動が海底全体を包んだ。驚いた「それ」は身を隠すべく手近に沈んでいた鉄屑へと潜り込んだ。その鉄屑は、かつて連合艦隊第二艦隊第一遊撃部隊(通称:栗田艦隊)に所属し、「最強の戦艦」と呼ばれていた「長門」のなれの果てであった。
戦後、アメリカ軍に接収されたこの戦艦はビキニ環礁で行われた原爆実験「十字路作戦」の為に、軽巡「酒匂」、そして多くの米艦船とともにその頭上で原爆を炸裂させられ、この海底に没していたのである。
続いて2度目の爆発が鉄屑全体を包んだ。「それ」は初めて経験する出来事に、しばらく鉄屑から這い出ることが出来なかった。
原爆実験は、この美しい海で繰り返されていた。
やがて海には静寂が戻ってきた。「それ」はおそるおそる鉄屑から海中へと出てゆくと、この珊瑚礁を後にした。
別の餌場に向かっていた「それ」は、突然自分の身体の変調に気がついた。何故か身体が熱く、身体の奥底から奇妙な力が沸いてくるのを「それ」は感じていた。
だが、先程よりもその体躯が膨らむように大きくなりつつあり、その体表も少しずつ変化をはじめていたことに「それ」はまだ気がついてはいなかった。「それ」はしばらくしてこのエニウェトク環礁に居着いていた。前に訪れた珊瑚礁とは違ってこの環礁には豊富な食べ物があった。「それ」はこの海域を遊泳し、己が生物としての生をまっとうしていた。
だが、その体躯は以前とはかなり変化していることに「それ」は気がついていなかった。身体はかなり大きくなり、背中にあった背鰭は岩のように硬くゴツゴツとしたものへと変わっていた。また、体表は黒ずみ、凹凸が激しくなり畝(うね)のような模様を形作っていたのである。
しかし、姿は変わっても「それ」の生物としての機能は、以前となんら変わることはなかった。その日も「それ」は餌を追って環礁の中を泳いでいた。以前よりも多くの餌を必要になった「それ」は、魚の群れを追って海上へと近づいた。
その時、それは起こった。海も空も突然真っ白い光に包まれたかと思うと、そのすぐ後にピンク色の煙が立ち昇った。海の表面は瞬時に蒸気へと変わり、それが空気を押し退け激しい衝撃波を発生させた。
衝撃波は海底まで到達し、また跳ね返った。海はシェイカーの中のカクテルのように激しく揺さぶられた。海中の生き物はその衝撃で次々と命を失っていった。かろうじて難を逃れた生物にもすぐに致命的な量の放射線が浴びせられた。海は瞬時に「死の海」となった。
人類初の水爆実験がこの日、米軍の手によってエニウェトク環礁で行われたのであった。
「それ」にも、同じように衝撃と放射線が襲った。激しい衝撃を受けた「それ」は身を痙攣させ、すぐに静かになった。「それ」の身体はゆっくりと海を沈んでゆき、やがて海底に横たわった。
「それ」の身体にやがて放射能を含んだ塵が雪のように降り注ぎ、その身体を覆って行った。そして、2年が経った。
1954年(昭和29年)3月1日 南太平洋マーシャル群島 ビキニ環礁
アメリカの威信を賭けた水爆実験が、ここビキニ環礁で行われようとしていた。使用される水爆は15キロトン、過去最大のものであった。半年ほど前、ソビエト連邦が初の水爆実験を成功させ、世界は「核の時代」へと突入した。
時の米大統領アイゼンハワーは、年末の国連演説の中で「アトム・フォー・ピース」を主張し、これをきっかけに大国は核兵器を次々と生産し始めたのであった。この時既に500基を超える原爆を有していたアメリカは、更にソ連に対し優位に立つ為に、より強力な水爆を必要としていたのである。そして、当初の予定通り、ビキニ環礁で水爆は炸裂した。水爆実験「ブラボー」のはじまりである。ビキニ環礁、いやマーシャル群島を包んだ放射能は、エニウェトク環礁でのそれをはるかに上回っていた。
海底で「それ」は目覚めた。「それ」はエニウェトク環礁を襲った放射線に耐え、2年を海底で眠っていた。その間に放射能は「それ」に驚くべき影響を与えた。「それ」の身体は50メートル程の大きさとなり、畝に覆われた黒い体表は鋼鉄の強さを有するようになっていた。そして、背鰭は3列に渡って岩のように首筋から尻尾にかけてを覆っていた。
「それ」はエニウェトク環礁をあとにすると、ビキニ環礁へ向かい海中を移動し始めた。「それ」は2年の眠りにより非常に飢えていたのだ。だが、放射能は驚くべき能力を「それ」に与えていた。いや、元々「それ」が持っていた能力が水爆の放射能により劇的に進化したのかもしれない。それは神のみぞ知ることであった。
ビキニ環礁に到達した「それ」は、海中の放射能をその身体に摂り込みはじめたのだ。海の生き物だけでなく放射能をも生きる糧とする。エニウェトク環礁で炸裂した水爆の放射能は「それ」をそのように変容させていた。
「それ」は自分の身体により強い力に満ちてくるのを感じていた。やがて、天啓のように「それ」はその力を解放させる術(すべ)を閃いた。
「それ」は身体を大きくそらせると全身に力を込めた。突如、背鰭が蒼白く発光をはじめた。「それ」はその顎を大きく開くと、力を海中に向けて放った。吐き出された放射能火炎は海中で激しい水蒸気爆発を引き起こし、海上に巨大な水柱を上げた。開放した己が力の威力に満足したかのように「それ」は一声吼えると、再びビキニ環礁を後にし、海中を移動しはじめた。
海上では放射能火炎が発した熱のために激しい風が吹き荒れていた。その様は不吉な未来を暗示するかのようであった。3 東京
果てしなく青い空が視界が広がっていた。その空のところどころに真っ白な雲が流れていた。雲の遥か下には紺碧の海がこれも果てしなく広がっている。
彼は、愛機のスロットルを捻ると更に高く上昇した。両翼の端から白い雲が筋を引くように産まれているのが見て取れた。彼の前方には僚機が彼の愛機と同じように雲を引きながら飛んでいた。
一式戦闘機「隼」。知覧を飛び立った彼らは、連合艦隊の「菊水作戦」のために沖縄沖に展開する米機動艦隊を目指していた。
昭和20年4月1日、遂に米軍は大挙して沖縄に上陸した。「アイスバーグ(氷山)作戦」のはじまりである。
その数、空母19隻、戦艦20隻、巡洋艦32隻、駆逐艦83隻、そして18万2000人の上陸部隊を輸送する為の艦船1300隻からなる大部隊であった。
これに対する日本軍は、陸軍第三十二軍指揮官牛島満中将を司令官とする陸軍部隊を中心とした約10万の兵であった。米軍の猛攻に沖縄は焦土と化し、兵だけでなく民間人にも容赦無く米軍の銃砲火と爆弾は降り注いだ。それはまさに「地獄絵図」そのものだった。
パニックに陥った兵士の中には民間人をわざと銃火の中に放り出し、その間に自分達の逃げ道を確保するものまで現われた。子供が、女子学生が、そして老人達が米軍の銃砲火の中に斃れて(たおれて)いった。
米機動艦隊艦船群を撃破すべく、陸軍第六航空部に所属していた彼は知覧基地を仲間とともに飛びたった。不思議とその心は穏やかだった。彼の命が祖国を、愛すべき故郷を護る礎となると思えば、死を賭けることを厭わなかった。
だが、それは突然に起こった。気がつくと僚機と自分との距離がぐんぐんと離されていく。彼はスロットルを振り絞った。しかし機体の速度はまったく上がらず、それどころか高度までもが少しづつ落ちていった。
彼は翼を振り、そして大声で僚機を呼んだ。僚機はすでに米粒のように小さくなり、空の彼方に消えようとしていた。
待ってくれ、俺を置いて行かないでくれ。お前等だけで行かないでくれ。彼は懸命にもがき叫んでいた。「ねえ、ちょっと!どうしたの、大丈夫?」女の声に、九重一馬(ここのえかずま)は、我に返った。「あ、ああ・・・」一馬は、曖昧に返事をすると布団の上に身を起こした。その身体には汗をじっとりとかいていた。
「さっきからうなされていたわよ。待ってくれ、とか何とか言って・・・」女は、文机の上に置かれた水差しからコップに水を注ぐと一馬に手渡した。
「何でもない。昔のことを夢に見ただけだ」ぶっきらぼうにそう言うと、一馬はぐいと水をあおった。「昨夜の酒が悪かったな。へんな事を思い出しちまった」コップを女の手に戻すと、一馬はまた布団の上に寝転がった。
昨晩、給与をもらった一馬はその足で浅草の呑み屋に立ち寄り浴びるほど酒を飲むと、そのまま吉原の馴染みの店にしけ込んだのだった。
九重一馬は三十三歳、元は陸軍の飛行機乗りだったが、一度機体トラブルにより特攻を果たせず、二度目の出撃の前に敗戦を迎えた経験を持っていた。彼は戦後、伝を頼って東京の雑誌社で働いていた。いや、故郷の大阪に居辛くなり東京へやってきたといったほうが正確だった。戦後しばらくを故郷で過ごした一馬だったが、「死にぞこない」と蔭で噂されているのにいたたまれなくなったのだった。復員後すぐに、栄養失調の為に一人娘を亡くしたことも彼の心に蔭を落としていた。妻とも別れ、一馬は東京に一人だった。
「昔のこと?兵隊の頃の話?」女が一馬の傍らに横たわりながら聞いた。女の名前はすず、といったが、もちろん本名ではないことは一馬はわかっていた。中肉中背、というよりも少し細かったが、胸と尻はぱんと張り、「男好き」のするいい女だった。顔立ちはど
ことなく若尾文子に似ている、と一馬は思っていた。年は、まだ二十歳を少し出たぐらいの年回りだろうと一馬は考えていたが、直接尋ねたことはなかった。一馬は昨年末にこの店に初めてきて以来、すずだけを相手にしていた。その理由は一馬にもはっきりとは判らなかったが、寝ていて心が安らぐ女、すずはそんな女だった。「戦争はいやね。思い出したくも無いわ」すずは一馬の胸に腕を回して言った。「あたしから全部奪って行った。家も家族も何もかも」すずが自分の身の上話をするのは初めての事だった。「お兄さんもやな事があったのね、きっと」すずは一馬の胸に軽く口づけた。
「戦争でいい思いした奴なんていやしないさ」一馬は右手をすずの頭にまわすとその髪をやさしく撫でた。すずは一馬の胸を枕にして話続けた。「長崎にいたの、あたしの家族。でも、あたしだけは宮崎のおじの家に預けられてた」
「長崎か。じゃあピカドンで・・・」「そう、ピカのせいで全部無くなったの。柱一つ残ってやしなかったわ、あたしの家」一馬の手の中ですずの頭がかすかに震えた。
「おじの家も食い扶持が多くて、あたしは居辛くなったの。それでこっちに出てきて働いたのよ。アメ公相手の酒場で十八だってウソ言ってね」「本当はいくつだった?」「十四よ」すずはペロっと舌をだして微笑んだ。
「店にはアメ公相手に商売する女もいたけど、あたしは絶対やらなかった。あたしの家族を殺した奴等と誰が寝てやるもんかってね」すずの裸の胸が震えていた。「新聞なんかじゃ、日本が悪かったとかなんとか書いてるけど、アメ公のやったことはどうなの?こないだだって、水爆で日本の漁船が・・・」
「もういい、辛い話はするな」一馬はすずの言葉を遮った。「戦争はもう昔話さ。それにアメリカにはさんざん儲けさせてもらった」
昭和25年に起きた朝鮮戦争の特需により日本は戦後不況から立ち直ったのだ。日本はアメリカの大補給基地としての役割を担ったのである。
「そうね、辛気臭い話をしちゃった。じゃあ、お詫びにサービスするわ」そう言うと、すずは一馬の上に覆い被さってきた。夜明け近くなって空が白々とし始めた頃、一馬は目を覚ました。気がつくと傍らに寝ていたはずのすずは、窓際に座って外を眺めていた。一馬はすずが何か口ずさんでいるのに気がついた。すずは誰に聞かせるでもなくかすれた小声で唄っていた。
「故郷の街焼かれ/身寄りの骨埋めし焼け土に/今は白い花咲く・・・」それは哀しげな歌だった。
一馬はただ黙ってその歌を聞いていた。4 硫黄島
太平洋をその本能の赴くままに移動する「それ」は、やがてマリアナ諸島北方の海域に差しかかった。この海域にくるまでの間に、大王烏賊や大蛸といった巨大生物が「それ」に戦いを挑んでくることがあった。しかし、いまや太平洋最強となった「それ」に叶う生物などいるはずはなかった。「それ」に立ち向かった生物は皆、バラバラに引き裂かれ、或いは放射能火炎により海中で焼き尽くされた。
やがて、「それ」は妙に気に障る振動を感じた。それは、あのエニウェトク環礁でも感じた、規則性のある振動、そして音だった。
南太平洋上にポツリと浮かぶ洋梨状の形をした周囲22キロの小さな島。かつて、日本軍とアメリカ軍との間で、太平洋戦争上最大の攻防戦が展開された島、それがここ硫黄島である。
栗林中将率いる硫黄島守備部隊とスミス海兵中将率いる上陸部隊との三十六日間に渡る戦闘の結果は米軍の死傷者数二万八六八六人、日本軍の戦死者一万九九〇〇人、捕虜一〇三三人で、激闘の末、米軍がこの地に星条旗を掲げたのだった。
現在、この島は米軍の管理する地となり、航空基地が設けられていた。夜とはいえまだまだ暑さの残る中で、オーク上等兵は、基地周辺の夜間哨戒の任務についていた。雲一つ無い夜空には大きな月が浮かび、それが水面を遥か沖まで晧晧と照らしていた。
オーク上等兵は煙草に火をつけると、地面に座り込んで一服しはじめた。もし、上官に見つかればどやしつけられるどころではないだろうが、今はその上官もベッドの中にいる時間である。訓練機のムスタングが基地から飛び立って行く轟音が響いた。今夜は夜間飛行訓練のある日だった。航空機の整備兵やパイロット達は忙しく基地の中を走りまわっているだろうが、オークにはとりあえず関係が無かった。
「まったく、こんな太平洋のど真中で見張りが必要なのかねえ?」オーク上等兵は海を眺めながら呟いた。この島へ赴任してきて3ヶ月、そろそろ故郷のバーモントに置いてきた彼女が気になりだした頃だった。「早く帰りてえよなあ」火山灰からなるこの島は、ただゴツゴツとした岩肌が続くだけで、何一つ面白いことのある処ではなかった。彼も、休日には海で釣り糸をたらす以外にまったくやることが無かった。
オーク上等兵は、1本目の煙草を投げ捨てると時計をチラッと見た。まだ時間はある。彼は2本目の煙草を取り出すと、口に咥えた。
胸ポケットからジッポを取り出そうとしたオーク上等兵の耳に、ザバアという波音が届いた。「うん?」彼は顔を上げて海を見た。
そこにはただ寄せては返す南の海があるだけだった。
「波か。そうだよな」煙草に火をつけて彼は言った。飛行訓練を終えて基地に戻ってくるムスタングが彼の頭上を通過していった。
「ご苦労さま」彼は海を眺めながら呟いた。
と、海のうえに白い三角波が上がっているのに彼は気がついた。その波はこの島へ向かって進んでいた。「何だ、ボートか?」彼は双眼鏡を取り出すと海面を眺めた。そこにはボートの姿はなく、ただ何か黒い塊のようなものが水面に顔を出し、それが島のほうへ向かって迫っていた。
「せ、潜水艦?」オーク上等兵は慌てて煙草を吐き捨てると、基地司令部へ向かって駈け出した。オーク上等兵の報告を受け、直ちに硫黄島基地全体に緊急事態が告げられた。全ての兵士が臨戦体制を取り、島に接近してくる謎の物体に備えた。
「照明弾の投下はまだか!」「今、投下されました!」その返事に基地司令のクラーク中佐は双眼鏡を謎の物体の接近地点へと向けた。パッ、パッと海面が明るい光に照らされた。その光の中で、何かが海面から聳え立つように波が盛り上がった。
「な、なんだ、あれは!?」クラーク中佐は双眼鏡を眺めたまま、驚きの声をあげた。海岸線で戦闘体勢にあったオーク上等兵も同じものを見て、仲間達と共に驚きの声をあげていた。
照明弾の灯りに照らされたそれは、潜水艦などではなかった。それは、黒い山のような直立した「生物」だった。
波間から姿を現したその生物はしばらくの間、基地の明かりを眺めてじっと海の中に立ち止まっていた。そこへ、哨戒から戻ってきた偵察機のエンジン音が響いた。その音に刺激されたように、突如その生物は辺りを震わすような叫び声を上げた。
「う、うわあ!」海岸線の兵士達はその声にパニックを起こした。数人の兵士が基地へ向かって逃げるように駈け出した。オーク上等兵も震える手で小銃を握ると、基地のほうへ駆け出そうとした。だが、意思とはうらはらに足がまったく動かなかった。
生物は、偵察機を追うように海岸へ上陸した。その目指す先には基地滑走路があった。
「なにをしている!砲撃だ!奴を砲撃しろ!」クラーク中佐は部下を怒鳴りつけた。何者かは判らなかったが、許可無く基地に近づくものは排除せねばならなかった。司令官にはパニックを起こす自由は与えられてはいない。砲兵隊がその生物に向けて砲撃を開始した。轟音が地面を震わせ、硝煙の匂いが辺りに立ち込めた。「あれだけデカい的だ、外すなよ!」「ありゃあ、一体なんなんだ!?」「俺が知るか!とにかく撃てばいいんだよ!」兵士達は迫り来るその生物に向かって砲を撃ちつづけた。
だが、その砲弾は命中するものの、まったくその生物にダメージを与えてはいなかった。その生物の進行速度は落ちるどころか、逆に怒りのためか更に早くなっていた。
「ダメだ!砲撃がまったくきかん!」「くそ、奴の身体は装甲板よりも硬いぞ!」基地の格納庫からP51戦闘機が数機、エンジンを回しながら姿を現した。戦闘機による対地攻撃をクラーク中佐が命じたのだった。パイロット達は滑走路に機体を誘導すると、スロットルを上げ、エンジンを更に回した。そのエンジン音が生物を更に刺激した。
「お、おい。あの背ビレを見ろ!光り出したぞ!」オーク上等兵の脇にいた兵士が生物を指差した。と、その生物の口から白熱した光が吐き出された。「うわあ!」その光が放つ熱は離れた場所にいるオーク達のところでも感じられるほどだった。
白熱光に直撃された戦闘機はたちまち、その熱で捻れ、溶け出した。パイロット達は慌ててコックピットから飛び出した。航空燃料がたちまち爆発し、P51ムスタング戦闘機は四散した。
その炎に照らされる生物の姿を改めてオーク軍曹は見た。黒く畝のある岩のような肌、背中に3列に並ぶこれもまた岩のような背ビレ、体長と同じかそれ以上ありそうな尻尾、その頭部ははっきりとは見えなかったが、無表情な瞳と開いた口の中に牙がならんでいるのが見て取れた。
「きょ、恐竜か?まさか、そんな。火を吐く恐竜なんて・・・」オーク上等兵は地面にへなへなと膝を着いた。燃え上がる炎の中で、その生物は再び吼えた。クラーク中佐は、サイパン基地へ応援を要請した。クラーク中佐の脳裏に少尉として参加したあの硫黄島攻防戦がまざまざと蘇ってきた。
「奴は・・・、日本軍の怨霊か・・?」サイパンを飛び立った戦闘機群が硫黄島へ到着した時、その生物は既に海中に姿を消していた。硫黄島基地は半壊し、多くの戦闘機や爆撃機が被害を受けていたが、不思議と兵士の犠牲は数少なかった。
クラーク中佐は本国に対し、何をどう報告してよいものか呆然と考えていた。5 嵐の夜
関東地方ではようやく梅雨が明けようとしていた6月末、南シナ海に発生した熱帯性低気圧はそのまま勢力を拡大し「台風10号」となった。この時期にしては珍しく日本本土に向かって進行してくる台風に、人々は、死者・行方不明者あわせて1200人を出す
被害を受けた3年前のルース台風を思い出していた。東京都大戸島村。ここは東京から太平洋をおよそ1100キロほど南下した海上に浮かぶ島である。室町幕府の時代に入植が始まり、現在では400人ほどの人々が住む。主な産業は漁業、水産加工業それに農業で、東京との連絡は月に一往復するフェリーのみという典型的な離島であった。
その日の夕方から激しくなり始めた風雨は夜半過ぎに本格的な嵐となり、大戸島は台風10号の勢力下にスッポリと包まれた。浜からは砂混じりの風が家々の壁や窓に激しく吹きつけていた。村の人々は台風の接近が予測されると、家の補強を行い、漁船を浜へ引き揚げ、被害を最小限に止めるべく努力をした。そして、今は家に閉じこもりひたすら台風が過ぎ去るのを祈っていた。
新吉少年の家も、父、母、兄、そして新吉少年の家族四人で居間に布団を並べまんじりともせずに嵐の夜を迎えていた。ゴウゴウと吹く風と時折風に飛ばされてきたのか何かが家の壁に激しくぶつかる音に新吉少年は母親のそばで震えていた。
「かあちゃん、大丈夫だよね?家が飛ばされちゃうなんてことはないよね?」「バカだね。昼間に父ちゃんと兄ちゃんで家の修理をしただろ。この家は大丈夫だよ。心配しないでもう寝な」新吉の母は、新吉の頭をやさしく撫でると、布団を新吉の身体にかけ直してやった。
「お前はいつまでも甘えんぼだな。そんなに風が怖いか?」新吉の兄がちょっとからかうような口調で、新吉の頭を軽くこずいた。
「だって・・・」そう言うと新吉は頭から布団をかぶって母親に抱きついていった。「しょうがないねえ、この子は」母親は赤ん坊をあやすように新吉の背中をポンポンと叩いた。母親の温かみの中でいつしか新吉は眠りへと落ちて行った。
外では嵐がますます激しくなっていた。真っ暗闇の中で、新吉はパチリと目を覚ました。外を吹く風はいくぶん緩やかになっていたが、それでもまだ木立を揺らすゴウゴウという音が響いていた。
「母ちゃん・・・」母親も、そして父も兄も今はぐっすりと眠っているようだった。新吉は布団をかぶり直すと、ぐっと目を閉じ眠りに戻ろうとした。だが、風の音が気になって再び新吉は目を開けた。新吉は風の音と共に、何か重いものが落ちるときのようなズズン、という音を聞いたような気がした。八幡山の崖が崩れたのかな?そんな事を考えていると、又もやズズンという音が今度は風の中ではっきりと新吉の耳に聞こえた。
「なんだろう?」新吉は小さく呟いた。その音は一定の間隔をおいて響いていた。
やがて、その音がする度に家の梁や柱が細かく震え出したのに新吉は気がついた。音と共にパラパラと天井から埃が落ちてきて、梁がみしみしっという音を立てて揺れていた。
カタカタと壁に掛けてある銛や竿までもが揺れ始めていた。「おい、起きてるか?」新吉の父親がむくっと起きあがり家族に声をかけた。「何の音だ?さっきから揺れてるぞ」父親は暗い中で辺りを見渡した。
ズズン!今度は家のすぐ近くで音が響いた。その振動で、神棚の供えてある破魔矢やお札、壁に掛けてある御神影の額が次々に床に落ちて行った。
「おい!家の外に出ろ!」父親が家族に向かって叫んだ。それと同時に、バキバキ、メリメリと音をたてて家の天井が崩れはじめた。「うわー!」「きゃー!」「かあちゃーん!!」新吉は訳の判らない恐怖に叫んでいた。
何かが新吉の身体に激しくぶつかり、気がつくと新吉の身体は柱に挟まれて動けなくなっていた。顔にかかる雨を感じながら新吉の意識は遠くなっていった。
TOPページへ