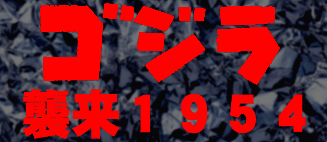
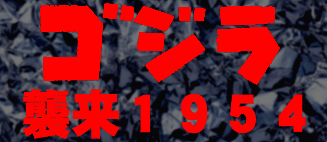
20 瓦礫
東京が燃えていた。
昭和二十年の敗戦から九年、ようやく復興を果たしつつあった首都・東京は、世紀の大怪獣ゴジラの襲撃の前に再び敗戦直後に引き戻されたかのような無残な姿と成り果てていた。
ゴジラの通り道となった、品川、銀座、赤坂、市ヶ谷、そして浅草の各地域の被害は特に甚大で、ゴジラの破壊により崩れ落ちた建物は数知れず、炎に焼け落ちた建物もまた同様だった。かろうじて全壊を免れた建物も炎によって黒く煤け、熱で多くのひび割れをその壁に走らせていた。
荒れ果てた東京のあちらこちらからはまだ黒い煙が上がり、誰も消し手がいない炎が焼け落ちた建物の瓦礫を更に燃やし尽くしていた。
『し号』兵器の活躍により奇跡的に被害を免れた千代田の森だけが、破壊の只中にあってその姿を元のまま止めていた。ゴジラによる恐怖の一夜がようやく明け、空が少しずつ白み始めた。崩れ落ちた民家の柱や壁板、そして家財道具が辺り一面に散乱し、元はカーテンだった布切れが風にバタバタとはためいていた。あたりに人の姿は無く、まるで幽霊の町さながらの状態であった。
突然、地面の一角からぎしぎしっという音が上がった。更に音と同時に、地面に散乱していた板切れが徐々に持ちあがり始めた。
そして何度か板切れは上下を繰り返した後、地面から持ち上げられた大きな板と一緒に横へと跳ね飛ばされた。板が跳ね除けられた後にはぽっかりと穴が開いており、そこから数人の男が顔を出していた。
「よっしゃ、やっと開いたぞ!」「まったく、何が乗っかってたんだ、一体?」
男達は穴に設けられた梯子を上って、次々に地上へと上がった。
「・・・ひどい有様だな、こりゃ!」「何にも無くなっちまってるじゃねえか!?」「ああ!オレの家が・・・!」
彼等はあたりの様子を眺めると一様に落胆した表情を浮かべた。穴からは男達に続いて、女や子ども達が姿を表わした。皆、頭に防空頭巾を被り、同じように疲れた表情をしていた。彼等もまたあたりの有様に気がつくとへなへなと地面に尻をついた。
やがて東京のあちこちで防空壕に避難していた人々が、危険が去った気配を察して地上へ登りだしていた。米軍の空襲から身を守る為に造られた防空壕は敗戦から九年経った現在でも数多く残されており、東京脱出が間に合わなかった人々の多くがその中に避難しゴジラの襲撃から辛うじて難を免れていたのだった。
しばらくして人々はなにかを決意したかのように、焼け残った防火漕からバケツリレーで水をくみ出して燃え残る炎を消し止め、火の延焼を防ぐ為に瓦礫をあちこちに避けはじめた。
やがて日が昇り、避難所に逃げていた人々も少しずつ自分達の住まいのあった場所に戻り始めた。中には、奇跡的に自宅の崩壊を免れた者もいたが、大半の人々の住まいは無残な廃墟と化していた。昼には小学校の校庭や公園などに赤十字の看護テントが立てられ始めた。怪我人たちが次々とそのテントの中に運び込まれ、医師や看護婦等による手当てを受けていた。炎により火傷を負った者や、崩れ落ちてきた建物の下敷きになり骨を折った者など症状やその怪我の度合いは様々であったが、彼等に対し献身的な手当てが続けられた。
「まったく酷い状況です」秘書からの報告を受けた総理大臣吉田茂は、ソファーに腰を下ろしたまま微動だにしなかった。
「民間人の死傷者は判っているだけで2,500名余り、焼け出された世帯数は5,000ではきかないでしょう。これから調査が進むに連れて、もっと被害者数は増えてくるものと思われます。更に自衛隊に至っては相当数の人命が失われた模様です。ゴジラとの戦闘に直接関った部隊は・・・」
「もう、いい」吉田総理は片手を挙げ、秘書の言葉を遮った。「詳しい事は書面にまとめてくれ。それよりも内閣の召集はどうなっている?全員に連絡はついているのか?」
ゴジラの襲撃により国会議事堂を含む国政機間が集中する赤坂近辺が重大な被害を受けた事もあって、各代議士たちはそれぞれが独自に避難を行っていた。中にはゴジラ襲来の数日前から地元に戻ってしまっていた代議士もいたが、大半は東京近郊の地方都市、特に熱海や伊豆近辺に避難していたのだった。
吉田総理も例外ではなく、熱海の一番大きな温泉旅館の、天皇陛下も宿泊した一番豪華な部屋に滞在していた。部屋には何台もの黒電話が置かれ、秘書官達が必死で各機関との連絡に追われていた。
「はい、木村防衛大臣、塚田自治大臣のお二人は防衛庁内におられますが、現場処理に追われて召集どころでは無い、との連絡が来ております。あとの方々は、この熱海や伊豆に避難された方とは連絡がつきましたが、軽井沢や地元に避難されている方の中にはまだ連絡がとれない人もおられて・・・」
「馬鹿者、早く連絡をつけんか!非常事態だということが判らんのか!」吉田総理はその秘書官を一喝すると、あわててその秘書官は部屋を飛び出していった。
「おい、車を回してくれ!わしは東京に戻る!」別な秘書官に向かって総理は怒鳴った。「と、東京へですか!?ですが、まだ安全が確認された訳では・・・」
「そんな事を言っていられる場合ではない!国家の一大事だと云う事がお前等には判らんのか!?他の連中にも伝えておけ。防衛庁内にて緊急の内閣会議を行うので直ちに東京へ戻って来い、とな!」日が経つに連れ、被害の状況は更に進んでいた。家を失った人々は、大きな寺や神社、学校などに設けられた避難所に集められ窮屈な暮らしが始まっていた。
浅草にある小学校もその例外ではなく、多くの住民が避難してきていた。その校庭の隅にある井戸では保健所から派遣されてきた職員が井戸に向かって筒型の装置を向けて何事か調査しており、その周りを子どもや大人が取り巻き不安げにその様子を眺めていた。
職員が汲み上げた水の入った桶に装置から伸びた筒を近づけると、ガガガという不快な音とともにその装置のメーターが大きく左右に振れた。
「くそっ!ここも駄目だ!」職員は急いでその水を人のいない場所に流すと、針金で井戸の汲み上げポンプを固定し始めた。
「おい、何してるんだ!?井戸を塞いじまったら水が使えないじゃないか!」「そうだよ、これから食事の支度をはじめなきゃならないんだよ!」住民達が口々に職員に文句を言いはじめた。
「いいですか、ここの井戸水を絶対に使わないで下さい!この井戸水は危険です、場合によっては命に関ります!」職員のその言葉に住人達は一様に顔を見合わせた。
「どう言う事だ?命に関るなんて」「ここの水はゴジラの吐いた毒に汚染されています。繰り返し言いますが、決してここの水を使ってはいけません。特に子ども達が勝手に水を飲んだりしないように、大人の方は十分注意をして下さい!」
「ゴジラの毒、だってえ?」井戸を取り巻く人の輪が一斉に後退した。人々は先ほど職員が流した水たまりを恐ろしげに眺めた。
「・・・でも、あたし達は水がいるんだよ。ここには赤ん坊だっているんだ。水を使うな、って言われたって・・・」一人の女性が誰に言うとも無く呟いた。「ゴジラの所在はまだ確認されていませんが、恐らく東京湾内にまだ潜んでいるだろうというのが大方の意見のようです」川嶋は何枚かの書類を佐伯に手渡しながら言った。
「これでは、一切の船舶は東京湾内に入ってくることはできません。出て行く方も同様です」
「まったくだな。ただでさえ救援物資が不足しているというのに・・・。茨城や静岡から陸送で持ってくるとなると時間も手間もかかり過ぎる」
「ヤツのせいで東京の機能はマヒしたに等しい状況です。・・・それと、一尉。聞かれましたか?国東陸将が更迭されるらしいですよ」急に声を落として川嶋が言った。
「更迭?ゴジラ殲滅の失敗に対する責任を取らされる、ってことか・・・。多くの隊員たちが犠牲になったとはいえ、今回のことは作戦の失敗などで片がつけられる話では無いというのに・・・」
「誰かが責任を取らねばならないのが組織ってものですからね。陸将もあと数年で退役だというのに」
「次は俺達が詰め腹を切らされる番かもしれんぞ」佐伯は部屋のドアのほうをちらと見て言った。
佐伯と川嶋のいる部屋の前には二名の自衛隊員が銃を携行して見張りに立っていた。二人もまた『し号』兵器の運用を巡って、この部屋に待機させられていたのであった。大阪。ここ梅田にある食品問屋には数日前から東京に向けての食料品の注文が次々と舞いこんでいた。東京に水揚げできない物資は大阪港にも回され、ここから陸送ルートで東京方面に運ばれるようになっていた。政府が特別調達するものを除いた殆どのも
のが、陸送費と手間賃とで、東京に届いた時点で元の何倍もの値がつけられていた。更に、困窮する人々の足元を見た悪質な商売も横行し始めていた。
問屋の倉庫のなかでは、社員達が食料の入った箱を数えていた。
「それにしても、こんな忙しいのは久しぶりやで」「ほんまや。なんぼ仕入れても注文でおっつかへんわ」
「しかし、こんなに儲かるなんてゴジラ様々やなあ。これからも時々東京を来てくれたらいいんやけど」「ホンマやな、あはは」
その二人の軽口を聞いていた番頭が二人を怒鳴りつけた。
「滅多な事いうもんやないで!東京では人死にも出とるんや。人様が苦しんではるのを喜ぶやなんて商売人のすることやないで!
今度そんな口をきいたら承知せえへんで、お前等!」
「す、すんまへん!」二人は首をすくめ、あわてて仕事に戻って行った。
「まったくなんちゅう奴等や・・・」その番頭には蒲田に住んでいる義理の弟夫婦がいた。しかしゴジラ襲来後、彼等とは連絡が取れなくなってしまっていた。九重一馬は、瓦礫が散乱する道を浅草に向かって歩いていた。途中までは自転車に乗ってきたのだが、倒壊したビルが道を塞ぎ、通れなくなっていたために止む無く自転車を乗り捨ててきたのであった。
あのゴジラ襲撃の夜、一馬は川嶋の運転で一度向島の避難所までやってきたが、そこの避難民の中にはとうとうすずの姿を見つけることが出来なかった。そこで、一馬は本日改めて吉原のすずのいた店の場所へと向かっていたのだった。
炎天下の中、瓦礫の道を二時間歩いて一馬は吉原へと到着した。だが、吉原に立ち並んでいたはずの建物の殆どは焼け落ち、街の様子は一変していた。何度か通ってきて憶えている筈の街がまったくなくなっており、一馬は自分が今吉原のどのあたりに立ってい
るのかすら判らなかった。仕方なく一馬は、何か目印になるようなものはないかとあたりを歩き始めた。
三十分ほど辺りを歩き回った時、一馬は道に座り込んでいる一人の女を見つけた。
「すまんが、ちょっと聞きたいんだが・・・」一馬はその女に近づくとそう声をかけた。振り向いた女の顔に一馬は見覚えがあった。それは女のほうも同じだったようで、女は一馬を見て立ちあがった。
「あんた、すずちゃんのところに来てたお客さんだろ?何でこんなところにいるんだい?」それは、すずと同じ店で働いていた女だった。一馬は店先で何度もその女の顔を見ていたのであった。
「・・・まさか、すずちゃんを探しに来たのかい?」女は一馬に問い掛けた。
「ああ、そうだ。物好きとでも何とでも思ってくれ。すずは何処にいるんだ?あんたたちと一緒なのか?」その一馬の問いに女は背を向けて、再び地面にしゃがみこんだ。
「おい?」一馬が女の肩に手をかけようとしたその時、女が答えた。
「すずちゃん、駄目だったんだよ・・・」
「駄目?駄目って一体どう言うことだ?すずに何かあったのか?」一馬は女の答えに、全身から血の気が引いていくのを感じた。
「あの子、あたし達が止めるのも聞かないでここに戻って来たんだ。部屋に家族の写真を忘れてきたって言ってね。それっきり帰ってこないんだよ、避難所にもここにも」
「すずが・・・」一馬は目の前の瓦礫の山を見つめて絶句した。
「馬鹿な子だよ、まったく。写真と命とどっちが大事だっていうんだい・・・」女は顔を伏せたままそう言うと肩を震わせた。
店のものの所在を書きとめた立て札が墓標のようにぽつんと瓦礫の中に立てられ、風に煽られて揺れていた。
(以下続く)
TOPページへ